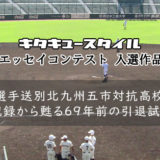エッセイコンテスト「第1回 キタキュースタイルカップ」 入選作品
「出戻り社員」が増えているというネットの記事を見かけた。かくいう私もその経験がある。というより、今まさに「出戻り」真っ只中なのである。しかも二度目の「出戻り」だ。人からは「二回も辞めてまた戻るなんて、相当この仕事がお好きなんですね。」とよく言われる。「はい、そうですね。」とは今更なんだか言いづらいが、認めざるを得ない。私はこの仕事を天職と思っている。恐らく死ぬまで離れがたい仕事だと思っている。
私の仕事は「小倉織」を現代に蘇らせた染織家・築城則子氏が監修する「現代の小倉織」ブランド「小倉 縞縞」の商品販売およびウェブコンテンツの作成だ。
小倉織は江戸時代からの長い歴史を持ちながら、地元でも知る人は限られている。小倉出身の私も、知人からこの仕事を紹介されるまではその存在を知らなかった。入社の前に地元の百貨店の売り場に下見に行くと、そこには今までの伝統工芸のイメージを覆す縞模様があった。目線の位置に置かれていたのは、「無彩キュービック」と書かれていたモノトーンの縞柄。その色と幅で構成された繊細なグラデーション。平面であるはずの生地の上には、驚くような立体感があった。自分の生まれ故郷にこんなすごい物があったのかと、私は雷に打たれたような衝撃を受けた。こが私と小倉織の出会いだった。
小倉織の特徴の主なところは、たて糸がよこ糸の約三倍の密度であるがゆえのたて縞の柄、綿織物でありながらなめし革のような独特の質感である。
しかしこれは、実際に見て、触れるとよく分かるが、文字だけではなかなか伝わるものではない。実際に見ること、触れることのできないお客様に、いかにこの生地の魅力を、伝えるか、私は朝から晩までそのことを考えた。
そう書くと、とても大変そうに聞こえるが、その作業は今までやって来たどんな仕事よりも遥かに楽しいものだった。
写真を撮るにしても、その立体感あふれる縞、滑らかな質感、そして多彩な色を再現す難しさに果ては無く、いつまでも撮っていたい気持ちになるのだ。そして自分なりにそ
れらが少しでも表現できたときの嬉しさは、それまでの時間と手間を一瞬で吹き飛ばす程のものだった。
文章を書くのは、写真を撮るよりもまた、楽しい作業だ。元々「日本語」が好きな私にとって、「緋橙」「うす紅」「梅薫」「翠風」などの美しい日本語の名前をつけられた生地に向き合い、生地の成り立ちや印象を言葉で綴るのは至福のときとしか言いようがなかった。
例えば「宵の水」と言う生地に向き合う時に、私は「宵闇」という本当の言葉の意味を知り、先人たちが見たであろう薄暗の風景に思いを馳せた。
「藍輪舞」や「藍万筋」といった生地には、奥深い藍の世界へと誘われ、日本人の季節や色彩への感覚の鋭さ、無限に広がる色彩表現に知れば知るほど驚かされた。
自身の経験や思い出、想像力を駆使して、言葉を綴り、生地を、縞を、深く深く感じてもらい、愛してもらいたい。
夢中になって書いては削ぎ落とし、それを延々と繰り返して、この言葉とリズムが柄にふさわしいと言うピースがはまったときの幸福感は、何事にもかえられないものであった。
顔を合わす事もないお客様に「記事を読みました」などと言われた日には天にも昇る心地であった。その上、尊敬してやまない築城則子氏に褒め言葉を頂いた日には、私は人目も憚らすに号泣した。幼い頃に願った詩人にはなれなかったが、私は夢をこの仕事で叶えて頂いたと言っても過言ではない。
世の中に美しい物は溢れている。しかし何故こんなにも小倉織が、縞が、胸を打つのだろうか。それは生地が出来上がるまでの本当に大変な工程を知ったからという事もある。たて糸の密度が高いがために傷も出やすく、だからと言って糸を太くすると、特徴を損なってしまう。一度は途絶えた織物を、古布のはぎれから蘇らせた築城則子氏、そしてそれを「現代の小倉織」として二度と途切れさせないと誓って進化させ続けるスタッフの筆舌に尽くしがたい情熱と苦労が、よりこの生地を気高く映すのだ。
コロナウィルスによる緊急事態宣言下、多くの方から小倉織への温かい言葉を頂いたが、私自身が先の読めない不安の中でも立ち続けられたのはこの美しく、強い布のおかげだった。
そして緊急事態宣言が解除された後、私は行きつけの美容室で膝に掛けられた小倉織の膝掛けの美しさに改めて心が震えたのだ。
横に見る縞のグラデーションは繰り返すこの世界の光と闇のよう。だが、縦に見る縞はただただ真っ直ぐに進んでいる一筋の光だった。どんな時もただただ真っ直ぐに進みなさいと、縞に教えられた、そんな気がした。
私は自身の生い立ちなどからも、ずっと生まれ育った小倉が好きになれなかった。だが、今は小倉織という世界に誇れる唯一無二の織物がある小倉に生まれて良かったと思っている。そして他の誰でもない、私にしかできない仕事を与えてくれた小倉織に感謝している。小倉織に出会わなければ、このような気持ちになることはなかった。
テキスタイルとテキストは語源は同じなのだと教えてくださった築城則子氏。これからも、私にしか織りなせない言葉たちで、この魅力をたくさんの人に伝えていきたい。
作者:池上 道子さん