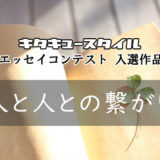エッセイコンテスト「第1回 キタキュースタイルカップ」 入賞作品
駅から出ると長い長い登り坂。見上げると派手な服や、ギラついたピアスを身につけた若者たちがやたらと目に入った。
これくらいの坂、自転車で登りきれないようでは、これからの大学生活に支障をきたす。
地元で餞別にと買ってもらったミニベロのサドルに勢いよくまたがると、テレビも洗濯機もないアパートの一室を目指して、僕はペダルを踏み始めた。
自分もいつかあんな風におしゃれをしたり友達と遊んだりできるようになるんだろうか。
不安と焦りでいっぱいになった頭を揺らしながら僕は坂を登りきり、部屋についたころにはじっとりと汗をかいていた。時は2003年。インターネットが一般的になりつつあったものの、まだまだSNSは流行しておらず、僕はラジカセと一通数円のメールを頼りに、初めて味わう孤独と向き合っていた。
後日、あの坂は「学園大通り」という名前であることを知る。どうりで若者が多かったわけだ。わざわざ大変な思いをしてまで、キラキラした人たちを見ることもあるまい。幸い僕が通う学校は学園大通りとは別の方向だ。しばらくあそこへいくのはよそう。そう思った。
予想とは裏腹に坂を登る機会はすぐにやってきた。いわゆる割のいいバイトにフラれてしまった僕は、藁にもすがる思いでバイト情報誌をめくり、やっとの思いで、とあるコンビニでのレジ打ちの職にありついた。そこは坂のふもとにある駅前の交差点で左折した先にある店。食っていくためには仕方がない。僕は腹を括り、自分とは別世界の住人たちが往来する坂を汗だくになりながら自転車で往復することに決めた。バイトをするにあたりジーパンはNGとのことだったので、僕はなけなしの3000円をチノパンに投入して、いよいよなりふり構わずコンビニバイトにしがみつくしかなくなっていた。
しばらく生活していると、学園大通りは折尾という街の中心のような通りであることがわかってきた。居酒屋、カラオケ、新古書店は暇を持て余す若者たちのたまり場で、サンリブに行けば生活に必要なもののほぼ全てを買うことができる。500円も出せば、胃袋がはちきれそうになるほど満腹にしてくれる食堂は、腹を空かしたものたちの救いだった。
自分で稼いだお金で服を買い、キャップを少し斜めにして浅くかぶれる程度にはおしゃれというものを学んだころになると、学校にもバイトにも、そして坂での生活にもだんだんと慣れてきた。友達もできた。サンリブのすぐ近くにあるジョイフルは、テスト勉強にかこつけた僕らの遊び場になり、夜な夜な集合しては馬鹿話に花を咲かせ、レポート提出が終われば大通りにあるコロッケ倶楽部で暴れるように永遠の愛を歌った。馴染めるかどうか心配していた頃の自分はもうすっかりなりを潜め、学園大通りは僕にとって家のような場所になっていた。いけば誰かに会える。話ができる。不思議な安心感があった。
いま思えば、あそこにいたほとんど全員が、僕と同じような気持ちで折尾にやってきて、同じように生活に慣れて、少しずつ友達を増やし、いつしか家族のような存在になっていたのだとわかる。派手に着飾ったり、よくわからない格好をしてみたり、大きな声を出してみたり、それは初めて地元を出たものたちの自己の証明であったのだろう。
何者でもなかった僕らの、ただただ過ぎ去っていった日々。あれこそが青春そのものだった。彼女を駅まで送ったことも、坂の途中で鍵を落として探しまわったことも、卒業旅行へ行く前の駅までの高揚感も、部活で結果を出せずに泣きながら登った日のことも。
誰が言ったか「長いようで短い」とは言い得て妙で、大学の4年間とはまさにその通りのものだった。最後に僕は学園大通りをできるだけゆっくり歩いて、次の誰かの4年間に想いを馳せながら、いってきますと別れを告げた。
著者:かきさん