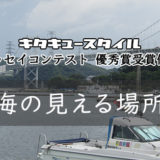エッセイコンテスト「第1回 キタキュースタイルカップ」 奨励賞受賞作品
1977年・秋 体育館の舞台袖。僕の心臓は荒々しく打ち、呼吸も早くなり、手も小刻みに震えていた。タンバリンを手にすると、振ってもないのにチリチリンと小さな音をたてた。舞台の演奏が終わり会場から拍手の音が鳴り響く。僕の足もカタカタ鳴った。
「ありがとうございます!次は本日のスペシャルゲストの登場です!」
拍手の音が聞こえる。僕は今にも噴火しそうなほどのぼせ上がった。舞台から友達のタオが早く出てこいと呼んでいる。僕は手招きに操られるようにフラフラと舞台へ出て行った。目に映るものはすべて夢の中の事のようだ。タオが笑ってマイクを差し出し僕はそのマイクを受け取って、ゆっくりと会場の方を振り向いた。体育館いっぱいの生徒たちが僕を見つめている。心と身体が現実の時間の流れに乗り切れていない。それぞれが勝手に逆流し始めている。
「曲は、吉田拓郎の「晩餐」です!」
タオはそう曲紹介をしてカウントをとった。
ワン・ツー・スリー
バンドが一斉に演奏を始める。僕は慌ててマイクを口元に運んだ。
その瞬間。最前列に陣取った恐ろしい形相の先輩たちが目に入った。
「しゃんと歌えよ、コラッ!」
声のパンチを数発浴びて、僕はクラクラしながら直立不動で歌い始めた。
〜ボクらわあ 夕食どきだったあぁ〜
自分でも驚くくらいの大きな声が出た。
しかし緊張のあまり目の前の恐ろしい先輩たちから目が離せなくなって、ほとんど、この人達のためだけに歌っている様な形になっている。
リーゼントの先輩がのけ反ってる。眉毛を剃り落とした女の子たちの目が大きく見開かれ、座ったまま後ろへずり下がっていく。
〜ボクらわあ 食べる時間だったからああぁ〜
角刈りで、おでこの両端を三角定規のように剃り込んだ体格のいい先輩が転がる。とさか頭が耳に手を当てて何か叫んでいる。平安貴族のような額をした女の子達は、長いスカートをバサバサさせて大笑いしている。
おっ? うけてる・・ のか? な?
歌いながら頭の中で僕が僕につぶやいた・・。
「晩餐」という曲はフォークでありながら、拓郎が声を張り上げて歌うブルースロックな歌である。「ライブ ’73」というアルバムに収められている。中学2年の秋、僕は文化祭でこの歌を歌った。演奏は親友のタオのバンドだ。まだカラオケなんてない時代、人前で歌うなんて生まれて初めてのことだった。
僕らの中学は製鉄所の煙たなびく北九州工業地帯の丘の上にあり、気性の荒い土地であったので、いわゆる”つっぱり”が沢山いた。僕らは青春のエネルギーを、荒ぶれさせるか、音楽で人気者になるかで、それを発散させた。でも僕には荒ぶる根性もなく、ギターも歌も上手くはない。教室ではいつも楽器を演奏できない連中と、箒をギターに見立てて騒いでいた宙ぶらりん男子だった。
そんな僕にバンドをやっている親友のタオが「文化祭で歌わんか?」と声をかけてくれた。僕は天にも昇る気持ちになった。目立ちたい!イコール、モテたい!のである。青春ビックチャンスなのである!文化祭のスター!きっとモテるようになる!単純爽快な僕はすぐにそんな妄想を描き二つ返事で快諾した。
思えば音楽と仲間達との友情はここがはじまりだったように思う。中学のひとつ上の先輩たちはカッコいいロックバンドをやっていた。レパートリーはビートルズ、ストーンズから吉田拓郎等々・・YouTubeもない時代、先輩たちが文化祭で聞かせてくれた音楽の世界は、憧れ以上に僕の全てを刺激した。
親友タオの兄がそのバンドの中心メンバーの一人で、タオを通して僕らの学年に先輩たちのマニアックな音楽世界と、ファッションの情報が流れてきた。ネットもない時代、中学生が仕入れる情報なんてたかがしれている。雑誌、テレビ、ラジオと言ったところだろう。しかしどうしてだろう・・先輩たちがあんなに音楽やお洒落に詳しかったのは・・。
僕らは今、知りたいことがあればネットを検索する。あの時代はパソコンもスマホもなかった。マニアックな情報源としては、ロックに関する専門誌や、楽器店の店員さんか、ラジオ、そして何より人との繋がりが大事だったように思う。ひとりでは知り得ない情報も人数が増えれば情報量も増える。僕らは直接会って色々な情報を交換しあった。人との繋がり。それがその答えのひとつかもしれない。
中学を卒業して高校生になると、行動範囲もぐっと広がって、僕らは住んでいる町から一歩踏み出し、もっと賑やかな小倉の街に繰り出していくようになった。
小倉魚町銀天街。
僕はここで沢山の出会いに恵まれた。なかでも忘れられない大切な場所。それは今ではもう老舗と言われるサンドイッチ専門店のOCMだ。1978年開店とのことなので、僕らが通い始めたのは開店早々の頃ということか。もちろん初めは先輩に連れていってもらった。サンドイッチは安くて美味しく、具材は様々にトッピングして自分好みのサンドイッチを楽しめる。そんなアメリカンテイストのお店だ。
週末になると必ず小倉に遊びに行ってはOCMに顔を出した。そこには同じような趣味の同世代の連中が沢山集まっていて次第に色々な高校の友達ができた。
当時のOCMには店の奥にジュークボックスが一台置いてあり、僕らは代わる代わるコインを入れては好きな音楽を流していた。知らない曲が流れると
「これ誰の曲?なんちゅう曲ね?」と誰ともなく尋ねると
「これ?これはブーム・タウン・ラッツのアイドンライクマンデーよ」
「月曜日はすか〜んちゅう曲」
「へー」
といった具合に誰かが教えてくれる。
そうかと思うとお洒落な格好をしてきた友達に
「その服何処の?」
「ほら〜 ここに書いてあるやろうも」
見ると胸に大きくロゴが書いてある
「MILKBOYね へ〜 かっこいいねえ〜」
そんな感じだった
あの頃、東京原宿の代々木公園ホコ天では竹の子族が流行っていた。竹の子族がなんだか知らなかったが、時を同じくして北九州の小倉城前の広場ではロックンローラー達がラジカセかき鳴らしてツイストやジルバを踊っていた。そして彼らも踊り終わるとOCMにやってきては、クリームソーダなんてロカビリーな飲み物を飲んでニコニコしてた。
僕のまわりの連中は大抵ビートバンドが大好きで、ダントツでルースターズの大ファンだったがロカビリーも好きになった。それはここOCMで彼らと友達になったからだ。
ここにいれば誰かが誰かを連れてきて、そしてそれは必ず誰かの友達だった。いつしかボクは通っていた高校の友達より小倉の友達の方が多くなっていった。スマホやネットもない昭和ど真ん中な時代、こうやって色々な仲間と出会い、新しいことやカッコいいことをグングン仕入れていった。僕らの情報源はいわゆる口コミで、いつも適度に偏り、適度に隠され、適度に創作されていた。でもそこがまた大いに想像力を刺激してワクワク過ごせたのだと思う。
OCMのある場所も良かった。魚町のアーケード街をぶらぶらして、東映会館をのぞいたりして喉が乾いたなあって思うとOCM。どうしたってここに帰ってくる。まるで部室のようなものだった。お金がなくても店に入れば誰か友達がいる。オーダーはセルフ方式なので、友達のテーブルに座ってればいつまでもいられた。
(ほんとはそんなのお店に迷惑な話なわけだけど・・。ごめんなさい!)
高校生になっても相変わらず僕はたいして楽器は弾けなかったが、OCMに出入りしてバンドをやってる友達は増えた。先輩はじめ同学年、後輩と知り合いは増え、色んなライブに誘われて行ったりするようになる。のちに東京でメジャーデビューするようなOCM仲間も何人か出て、彼らの活躍は自分のことのように本当に嬉しかった。
その後、僕は高校を卒業し上京。それ以来、故郷北九州に暮らしたことはない。だが僕の人生はあの時のOCMの思い出や、この街にずっと支えられていた。この街での出会いが僕のアイデンティティになったし誇りになった。北九州を離れてもずっと北九州が心の支えだった。それは50代後半になった今も変わらない。思えばOCMで楽しく過ごしたのはたった3年あまりだ。青春時代の濃密な数年が長い人生を支えることもある。
さて、中学2年の秋晴れの文化祭。ボクは暴走機関車のように歌い終わって体育館を出ると、あの恐ろしい先輩たちに呼び止められ、いきなり羽交い締めにされた。
「キサン!あの歌はなんか!」とさか頭が言う。
「スピーカーのポコポコしようとこが、おまえ!ダァーっち出っ放しぞ!こら」
「タンバリンはねえ、振らんと、音がせんのよぉ・・」平安貴族女子がニヤニヤ笑う
「い、いや、そんなん言われても・・」僕はもがきながら呟いた。
「耳が破れとるごとあるぞ!病院行くけ金出せ」
「すんません!すんません!」
そう言って僕は先輩の腕を振りほどいて逃げ出した。
「吠えるな!歌え!こん馬鹿が〜!」
笑い声と罵声が容赦無く背中に突き刺さる。
僕は校舎へと続く渡り廊下を全力疾走で走って逃げた。走りながら何故か急に可笑しくなった。無性に可笑しくなって声を出して笑いながら走った。
そう、あの時、本当に僕は馬鹿であった。でもそれは幸福な意味でだ。
今でもあの日の僕がたまらなく可笑しい。
しかし、あの日とOCMの日々があったからこそ、今も笑いながら人生の渡り廊下を突っ走っていけるのだ。北九州よありがとう! felicità!
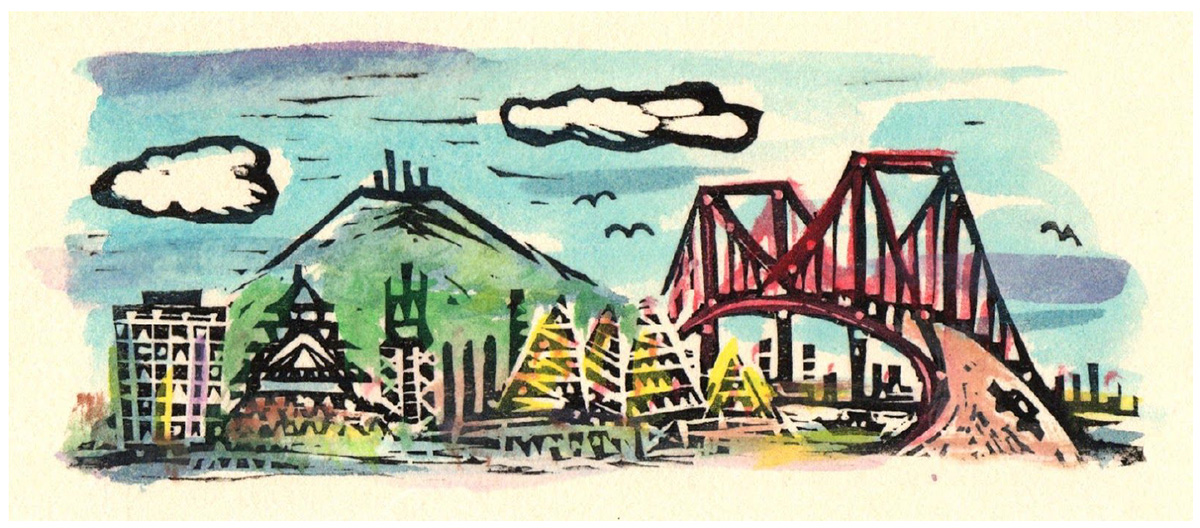
作者:南柯コーカさん