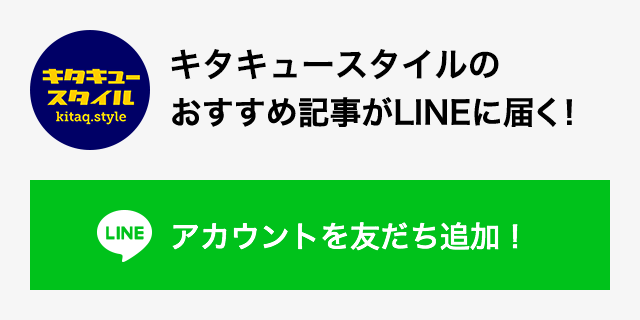令和5年の薬物事犯者は13,815人と発表されており、そのうち10代~30代の割合が8割を超えています。従来の街頭啓発活動では若者層に十分届いていない現状を受けて、北九州市が新たに開始した「薬物乱用防止を考える啓発プログラム」。その第1回ワークショップが7月11日(金)に北九州市立高校で行われました。
高校生自らが薬物乱用防止策を考え、実際に啓発活動まで行うこの取り組みで、生徒たちはどのような課題を見つけ、どんなアプローチを模索していくのでしょうか。
市の新たな取り組み「薬物乱用防止を考える啓発プログラム」
若年層を中心とした薬物乱用の危険性が社会的問題となる中、北九州市ではこれまで街頭啓発活動を中心に薬物乱用防止に取り組んできました。しかし、若者層に対するさらなる啓発を図るため、今年度から新たな取り組みとして「薬物乱用防止を考える啓発プログラム」を開始。若年層に効果的に響く啓発方法を若者自らが考え、取り組む機会を設けました。
このプログラムは北九州市立高等学校の1年生約200名を対象とし、7月から翌年3月まで段階的に実施されます。7月11日に行われたのは、その第1回ワークショップで、1時限目と2時限目を使って実施されました。
若者の大麻事犯が7割超 データで見る現状

この日の授業では、厚生労働省が発表している「大麻事犯における検挙人員の推移」のグラフが生徒たちに示されました。生徒たちがグループワークで分析し、次のような発表が行われました。
「年齢に関わらず検挙人数が増加している中でも、特に30歳未満の検挙人数が顕著に増加している」「平成30年度時点で30歳未満の検挙者が全体の5割を超えている」「令和5年になると30歳未満の検挙者が7割を超えている」。
大麻事犯の約7割が30歳未満の若者によるものという現実がわかりました。授業を担当した北九州市立高校の井上鷹先生は「若者の検挙者の増加が大麻全体の検挙者数の増加に直結している」と指摘しました。
知識はあるのに事犯は増加 浮かび上がる矛盾
授業に先立って行われた事前アンケートでは、生徒のほぼ全員が「大麻は違法薬物であることを知っている」、そして「薬物乱用が心身の健康や社会に及ぼす影響について理解している」と回答していました。
小学校、中学校と薬物乱用について学習を重ね、保健の授業や講演会でも繰り返し危険性を学んできた世代です。それにも関わらず、なぜ同世代の若者たちが大麻に手を染めてしまうのでしょうか。
井上先生は「昨日のニュースでも北九州市で16歳の少年が大麻で逮捕されている。君たちと同じ年代の人がなぜこんなことになってしまうのか」と問いかけました。
生徒が分析する大麻事犯の背景

授業後半に行われた「ワールドカフェ」で、生徒たちは次のような分析を行いました。 ワールドカフェとは、カフェのような雰囲気の中で参加者が自由に席を移動しながら対話を重ね、多様な意見を交換する手法です。今回は各グループの代表者1人がその場に残り、他の生徒たちが興味のあるテーマのグループを訪れて議論を深めました。
この対話を通じて、大麻を使用する個人的要因として、自己肯定感の低さや感情のコントロールの困難さが挙げられました。さらに、ストレスや疲労への対処法として薬物を選んでしまうケースや好奇心、「自分だけは大丈夫」という過信なども要因として考察されました。
大麻を使用する個人的要因として、自己肯定感の低さや感情のコントロールの困難さを挙げました。さらに、ストレスや疲労への対処法として薬物を選んでしまうケースや好奇心、「自分だけは大丈夫」という過信なども要因として考察されました。
社会的要因については、SNSやインターネットの普及により薬物に関する情報や入手方法が容易に得られるようになったことが大きく影響していると生徒たちは見ています。友人からの誘いや周囲の環境、薬物を使用する仲間とのネットワーク形成、社会的孤立感や居場所のなさなども、若者が薬物に手を染める背景として議論されました。
注目すべきは、「薬物の危険性は学習で理解しているが、実際に経験したことがないため現実感が薄い」という指摘でした。知識として知っていることと、実感として理解することの間には大きなギャップがあることがわかりました。
従来の啓発活動の課題も明らかに

授業では、6月14日に小倉駅JAM広場で実施された「ヤング街頭キャンペーン」の事例が紹介されました。この活動は薬物乱用防止を呼びかける目的で、ティッシュやうちわを配布しながら啓発を行うものでした。
しかし、当日キャンペーンに参加した生徒たちからのアンケートではさまざまな課題が浮かび上がりました。若者を対象とした活動だったにも関わらず、若い年代の人ほど受け取ってくれる人が少なく、配布したうちわやティッシュを捨てる人もいたそうです。さらに、面白がって冷やかす人もいるという状況でした。
つまり、最も薬物乱用防止のメッセージを届けたい若者層に、従来の啓発方法では響いていないということがわかりました。
夏休み課題から本格的な活動へ
この現状を受け、生徒たちには夏休みの課題として「より若者に効果的な薬物乱用防止策の考案」が出されました。啓発運動の部、ポスター等の部、その他の部の3部門のどれかを選び、薬物乱用防止策を考案するというものです。
この夏休み課題の成果は、9月上旬の第2回ワークショップでクラス発表され、各クラスから代表が選出されます。その後、代表メンバーが中心となって、啓発グッズやポスターの制作、啓発動画の作成を経て、最終的には来年6月に実際の啓発活動を展開する予定です。また、本プログラムでは11月上旬に、薬物乱用防止をテーマとした講演会と演劇を全校生徒約600名を対象に開催予定です。
当事者世代の視点から生まれる新たなアプローチ

この「薬物乱用防止を考える啓発プログラム」は、従来の大人主導の啓発活動とは異なる取り組みです。高校生が主体的に「自分ごと」として薬物乱用防止を考え、同世代に響く方法を模索することで、より効果的な啓発活動の実現を目指しています。
生徒たちが「現実感の薄さ」を重要な要因として挙げたことは、知識の詰め込みではなく、より身近で実感できる啓発方法の必要性を示しています。今後の活動でどのような具体的なアプローチが生まれるかが課題となるでしょう。
高校生自らが企画から実施まで主体的に関わるこの取り組みでは、デジタルネイティブ世代ならではの発想や、同世代の心に響くメッセージの作り方など、大人とは異なる視点からの提案が期待されます。